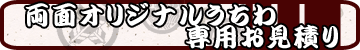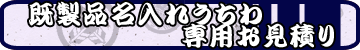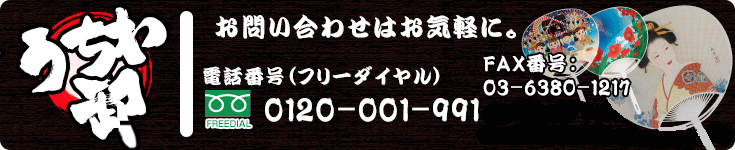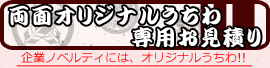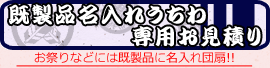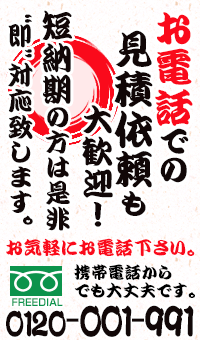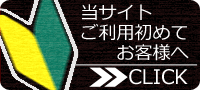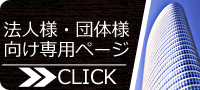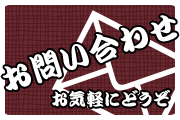【うちわ卸】をご覧頂き有難うございます。
夏の祭イベントのノベルティや配布の定番、うちわを名入れ・プリント技術を駆使し、お客様に満足して頂けるよう制作販売致します。
低コスト・短納期をコンセプトに掲げ大量ロット時では業界最安値を意識した激安・格安の団扇の特注オリジナル制作を致します。

トップページ>京と江戸のうちわ
日本伝統の団扇(ウチワ)や扇子(センス)のデザインには大きく分けてふたつ、制作場所が京か江戸かで違いがありますが、それは具体的にはどういった違いがあるのでしょうか。
それぞれの土地や時代背景、文化、流行などさまざまな観点から、そのウチワの違いを考えてみたいと思います。
特にこれからオリジナルデザインによるうちわの作成販売をお考えの方の参考になれれば幸いと考えております。お時間のあるときにでも是非一度、ごゆっくりご覧下さいませ。
京うちわ
小中学校の一般的な歴史の授業でも習ったように、京に都が置かれたのは西暦794年の平安時代の頃のことで、これは鎌倉幕府が成立する西暦1185年まで約390年間続き繁栄していたとされています。この時代は、遣唐使の廃止により日本独自の文化が成長し始めた時代であり、当時の流行としては優雅で煌びやかで華やかなものが好まれ製作されておりました。
よって、当時のそういった流行を汲んだデザインで制作されたものを「京うちわ」と呼ぶのだと思われるかもしれませんが、実のところそうではありません。
この平安時代から更に200年ほど進んだ南北朝時代、中国や朝鮮半島沿岸などを荒らしまわっていた倭寇(わこう)と呼ばれる日本の海賊がおりました。彼らが奪った様々なものは近畿地方を中心にこの日本へと持ち込まれましたが、その中に、地紙の中に多くの竹骨をもつ朝鮮団扇と呼ばれるものがあり、それが更に改良され京都に別荘を持つ貴族の間で持て囃されるようになったものこそが、「京うちわ」なのだそうです。
中骨と柄が一体ではなく、挿柄と呼ばれる後から取り付けられる構造が特徴で、しかしウチワのデザイン的にはやはり平安時代に流行していたような華やかな色使いのものが多いとされています。
江戸うちわ
江戸時代に入ると、それまで貴族などの上位の人々の間の道具であった団扇は次第に安い価格で一般庶民にも広まっていきました。そして江戸の町民文化の流行の中で生まれたのが、この「江戸うちわ」です。
この特徴は浮世絵の技術を取り入れられており、風景画や美人画、歌舞伎役者などがモチーフにされたものが多く、また京うちわと比べるとやや落ち着きのあるシックなデザインが多いように見受けられます。
またウチワ形状は丸柄と呼ばれるもので、細かく裂いた竹を糸で編んで扇形にし、窓と呼ぱれる根元の両端から編んだ糸の房をたれ下げ、格子模様の美しい半円の窓が特徴となっております。
現代の通販型専門店であります当店においてはどちらの特注団扇のタイプにせよ、どんなデザインにせよ、またどんなオーダーにせよ、精巧にプリント印刷することが可能であり、激安価格で作成致しますのでお気軽にご利用下さい。
またデザイン製作も自体も格安で承っておりますので、ご相談下さい。